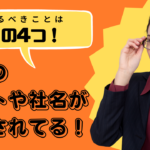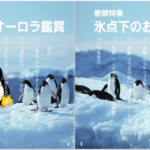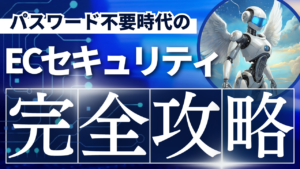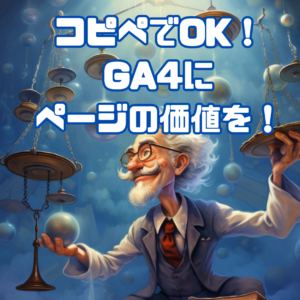|
世界エイズデー 、 twitter の赤い画面と仕掛け
今日、偶然、twitterにログインしようとしたところ(2009/12/01 午後5時)
ログイン画面がこんな風に赤くなっていました。
クリスマスかな?とおもったら、
1 DEC is World AIDS day. Help turn Twitter (RED). Follow @JoinRED to find out how.
12月1日は世界エイズデー。と、書かれていました。
さらに、#red のハッシュタグを入れると、
webの投稿文字が、キャンペーンカラーの赤に染まります。
 |
どうやら、NIKEと(RED) x twitter のHIV/AIDS基金キャンペーンのようです。
今回のキャンペーンの主旨
端的にいえば、「赤い靴ひもを締めて、HIV/AIDSを撲滅しよう」というキャンペーン。
NIKEが世界各地で販売する「赤い靴ひも(シューレース)」をつけて
基金に参加しようという呼びかけを、著名なサッカー選手達が呼びかけます。
公式サイトでは、twitter、facebook、メールなどを用いて
コミュニケーションを持ち、キャンペーンを告知。
私達にできること
この赤い靴ひも(シューレース)は、海外のNIKEのショップでは 4ドルで購入できるようです。
 |
日本のオンラインショップやリアル店舗での情報は探してみましたが、ありませんでした。
(2009/12/02追記:実際には国内も店舗販売しているようです)
公式サイトにキャンペーンのWidget ツールがありました。
(RED) というブランドについて
恥ずかしながら、(RED) の存在を深く知らなかったのですが、
2006年に、バンド:U2 のボノ と ボビー・シュライダー (NGO団体DATA)が設立以来、
アップルや、デル、スターバックス、ギャップ、そして今回の NIKE などがパートナーとなり
総額1億4000万ドルを、アフリカの HIV/AIDS問題 のために集めたという非常に大規模なプロジェクトのようです。
twitterの HELP TURN が、コミュニケーションツールとして 最左に位置しているのが
印象的です。
 |
(RED)公式サイト:http://www.joinred.com/
twitter TOPページの効果?キャンペーンの伝播速度がすごかったです。
・ハッシュタグ #red を付けたり、
・プロフィール画像に赤いリボンをつけたり、
・@joinred の発言をRTする
などで
このキャンペーンを広めようというしくみ。
驚いたのは、
告知から3分も経たないうちに、
秒速300件くらいで世界中がRTしはじめたこと。
#red の検索結果が、またたくまに増えて行きました。
個人的なHIV/AIDSへの印象
 |
| From webmarketingA picasa |
これを見て思い出したのが、
今年の3月に行われた、谷村新司さんのココロの学校 というコンサートに伺ったときのこと。
フジテレビさんとのコラボをされていて、エイズの現状のムービーを20分ほど見ました。
毎日、約4千人の若い男女と子供達がエイズで亡くなり
改善しようの無い貧困と、
その家族を支えるための出稼ぎが、
皮肉にも、アフリカの子供達に、深刻なHIV/エイズ問題を生んでいる現状を
初めて知りました。
自治体だけでは改善が不能、外部からの支援が必要だと感じました。
・ウィルスであるHIV
(Human Immuno-deficiency Virus:ヒト免疫不全ウイルス)
・それに感染した合併症状態のAIDS
(Acquired Immune Deficiency Syndrome:後天性免疫不全症候群)
■(RED)キャンペーン:主催者のひとりの声
今回、サッカーというスポーツを通じて、この活動を広め、
スポーツシューズの靴ひも(シューレース)を
NIKEの赤い4ドルの靴ひもに代えることで、
この基金に参加しよう、というキャンペーンですが、
(赤い靴ひもをきっかけに、新しいNIKEスニーカーも買ってもらうというアクションもありますが)
なにか背中を押してくれるキーワードがあればな・・・と思っていたら、
このキャンペーンの主催の一人でもある、
世界基金のミッシェル・D・カザツキン教授の言葉が心に残りました。
「シューレースを身につけていることは、他の人を思いやる気持ちを表します。
これによって、日々感染のリスクにさらされ、あるいはHIVの症状に苦しんでいる
数百万人の人達を守り、治療することができるのです。」
動かしようのないこの環境を、
世界中の有志で支えよう、伝播しよう、と言う今回のキャンペーンに、
公式サイトの、topツールとして twitterが位置しているのは益々の威力を感じると供に
web以外の様々なクロスメディアの戦略が、マーケティングとして大切な勉強になりました。
今回、残念ながら、日本では、文字が赤くなるよ、程度の話題で
あまりチャリティー(ここに違和感を覚える方もいらっしゃるのかも)にまでの反応がなかったようですが・・・。
日本語ページが無かったり、これからでしょうかね。